これからの時代、シニア人材は単なる“経験者”としてではなく、変化の時代に柔軟に貢献する“共創のプレイヤー”として再定義されていくべきだと感じています。そのために、Shared LeadershipとCo-learningという2つの文化は、シニア活躍の土壌として極めて重要です。そしてさらに──「現場感」を取り戻すこと。この3つが揃ってこそ、シニア人材の可能性は大きく花開くと確信しています。
Shared Leadership──シニアを主役にも脇役にもできる柔軟な組織へ
Shared Leadershipの思想は、「役職」にとらわれない組織づくりを促します。その中では、年齢や肩書きに関係なく、プロジェクトや状況に応じて“最も力を発揮できる人”がリーダーシップを担う仕組みが生まれます。
こうした文化が根付けば、シニア人材も「過去の役職」に安住することなく、自らの知見を活かす場を見出し、常にアップデートを意識せざるを得ません。
ポスト不足や“年功序列のしがらみ”といった問題に悩む前に、Shared Leadershipという設計思想を、組織の初期段階から取り入れていくことが有効ではないでしょうか。
Co-learning──老いも若きも、共に学ぶことが当たり前の文化へ
Co-learning、つまり“共に学ぶ”という文化もまた、シニアにとって大きな救いとなる考え方です。プライドゆえに一人で必死に学ぼうとするのではなく、立場に関係なく共に学び合うことが組織の当たり前になることで、心理的安全性が確保されます。
その環境で、シニアが自ら積極的に学び直しを実践する姿は、若手にとっても尊敬の対象になり得ます。かつて受験や資格取得などで培ってきた「集中して学ぶ力」を、もう一度発揮する時が来ているのです。
そして、最も重要な視点──現場感を取り戻せるか
Shared LeadershipとCo-learningが「土壌」だとすれば、現場感の回復は、シニアが“再び花を咲かせる”ための栄養源です。
現在、多くのシニアがマネジメント職を長年務めた結果、現場から離れてしまい、「現場の感覚」を失っていることが、再就職や新たな挑戦を難しくしています。
たとえば、かつて大企業で活躍していた人が中小企業に転職しても、
- 上から目線が抜けない
- 現場の実情に合わない高度な仕組みや理論を語ってしまう
- 中小企業の「弱者の戦略」に馴染めず違和感を生む
──といったことが原因で、結果的に現場との軋轢を生み、離職に至ってしまうケースは少なくありません。
シニアの持つ経験は本来、現場にとって大きな財産です。にもかかわらず、それが伝わらないのは「経験が現場から切り離されてしまっている」からです。
だからこそ、どこかの時点で“現場感”を回復する機会を設けなければ、次のキャリアの選択肢が大幅に狭まってしまうのです。
現場感の回復を支える仕組みを、今こそ
そのために必要なのは、「単なる再配置」や「名ばかりのアドバイザー」ではありません。明確な役割と責任を持ち、現場と共に歩む立場──例えば“伴走型アドバイザー”というようなポジションです。
これは、若手とともに現場に立ち、時に指導し、時に学び合いながら、組織の実情に即して貢献できる立場。マネジメントと実務の両方を理解しているからこそできる“プロフェッショナル”な役割です。
このようなポジションを2〜3年経験したのちに、外部の中小企業や地域のプロジェクトに関われば、ミスマッチは大幅に減り、活躍の幅が広がるはずです。
「伴走型アドバイザー」以外にも、技術後進の育成専門職、地域連携や産学連携のハブなど、現場に戻る選択肢をもっと用意すべきではないでしょうか。
シニアが再び組織の力になるために──3つの柱
これらを踏まえると、シニア人材が活きる組織をつくるためには、次の3本柱が鍵になると考えます。
- Shared Leadership──年齢や立場にとらわれない柔軟なリーダーシップ
- Co-learning──世代を超えた学びの文化の醸成
- 現場感の回復──シニアが再び“プレイヤー”になるための再接続
この3つを意識した組織設計が、変化の時代を生き抜くチームをつくり、シニアの経験を未来に活かす鍵になると信じています。
シニア活躍の施策ポイント
上で述べた、3つの柱から、シニア活躍のためのポイントをまとめてみました
1.リスキリングと実践の機会を制度化
・年1回、現場課題をテーマとしたプロジェクトへの参画を義務化
・若手との混成チームで、最新のツールや情報に触れる
・コ・ラーニング(共に学ぶ)文化を体現する場として機能
2.“現場経験”を活かす新たな役割設計
・「管理職経験+現場経験◯年以上」の人材に限定した“伴走型アドバイザー”制度
・現場実務のアップデートを求める仕組みにより、経験を生かしつつ成長を継続
・「現場を忘れない管理職」文化の定着へ
3.経験知の可視化と共有の仕組みづくり
・「シニアの知恵バンク」や「経験ナレッジ共有会」を定期開催
・「なぜそう判断したのか」といった意思決定プロセスの共有に重点
・“知のライブラリアン”としての活躍の場を創出
4.心理的安全性と挑戦を後押しする組織風土へ
・「成長は年齢に関係なく続く」ことを価値観として明文化・浸透
・年齢に関係なく「学び・挑戦が当たり前」という雰囲気づくり
・人事評価に“学習・挑戦のプロセス”を組み込む
5.ライフステージに応じた柔軟なキャリア選択肢
・一律の役職定年ではなく、以下のような多様な道筋を整備↓
- 現場プレイヤーへの転換
- 後進育成の専門職
- 経営アドバイザー(現場との接続を条件に)
- 地域や産学連携との橋渡し役
6.価値貢献型マインドへの転換
・肩書きや年収よりも、「今、どんな価値を提供しているか」を重視
・シニア世代自身が“価値を発信する存在”となることが、組織文化の鍵
組織ラジオでも語っています
Shared Leadership、Co-learning、そして“現場感の回復”について「組織ラジオ」でも語り合っています。ぜひ聴いてみてください。下のタイトルをクリックするとポッドキャストに飛びます。
■第236回組織ラジオ「シニア人材を活かすShared Leadership、Co-learning、そして・・」





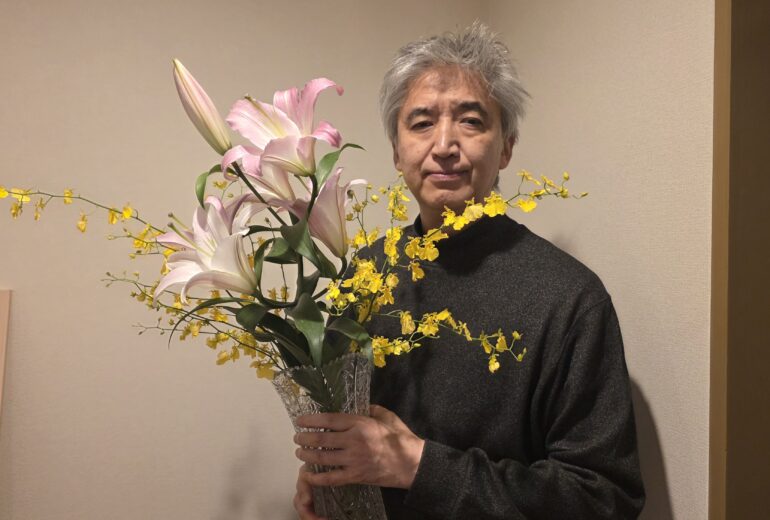
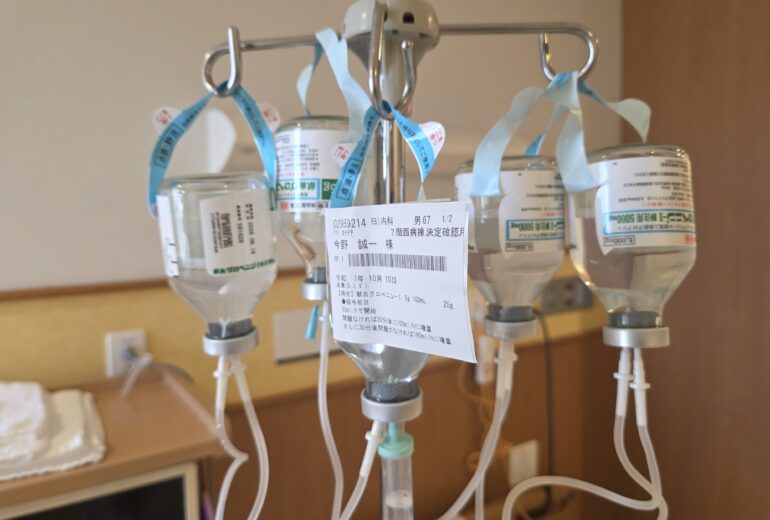
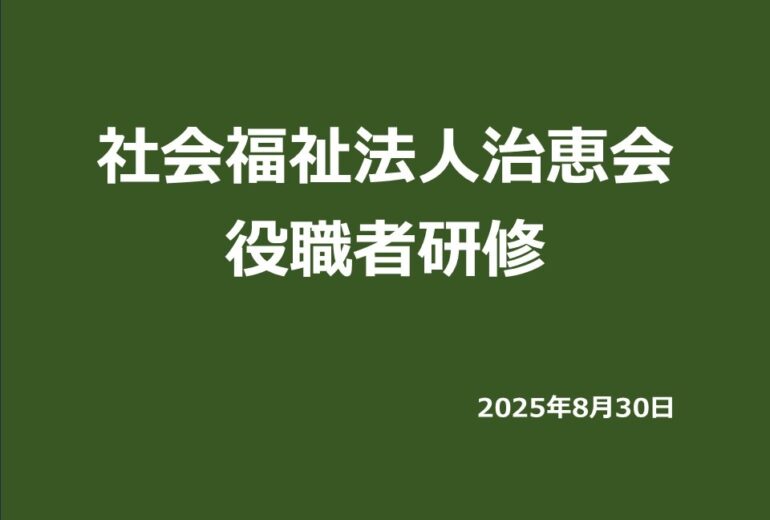
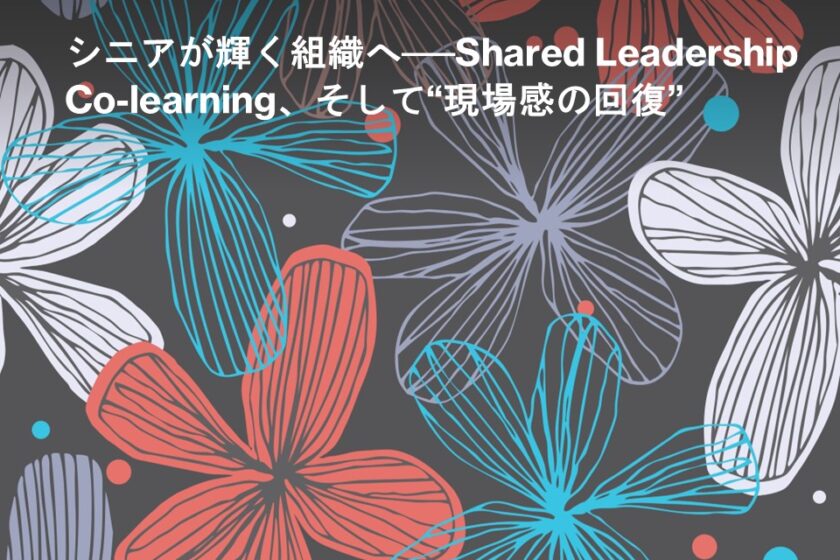








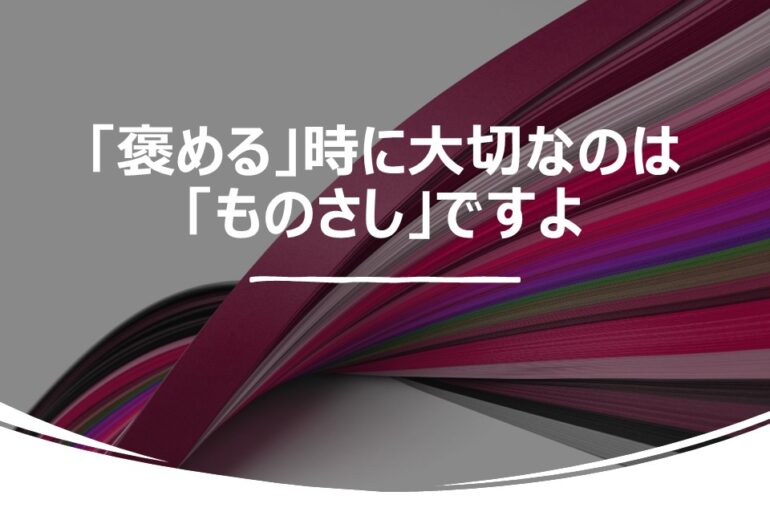
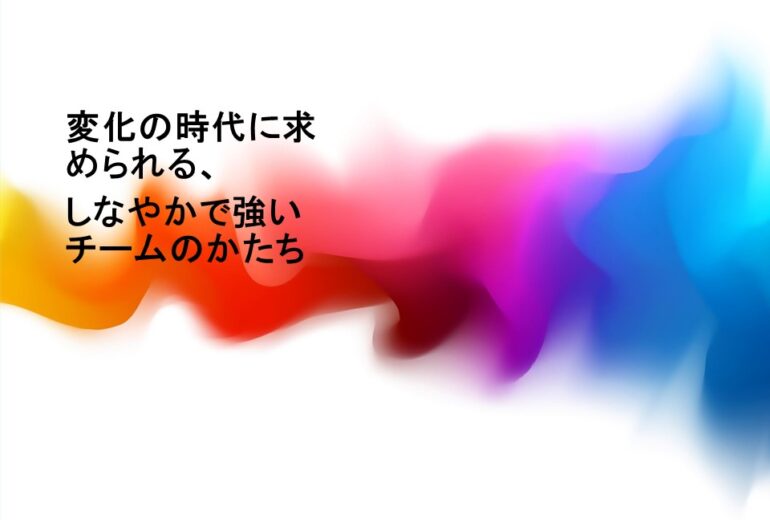
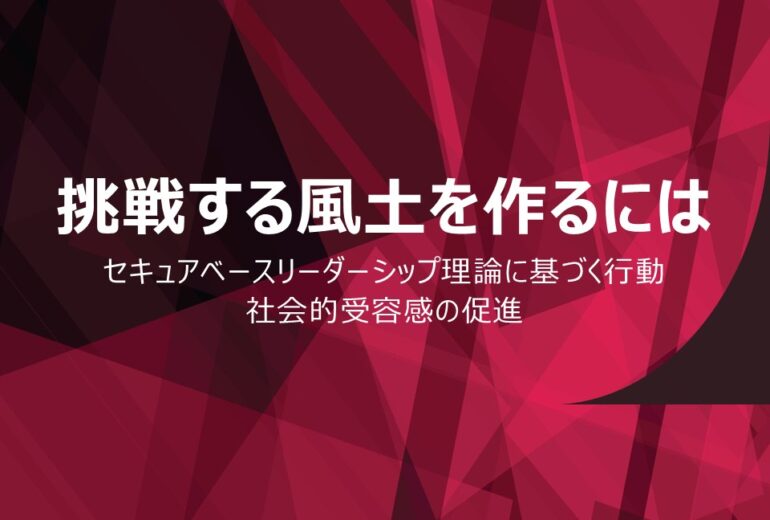
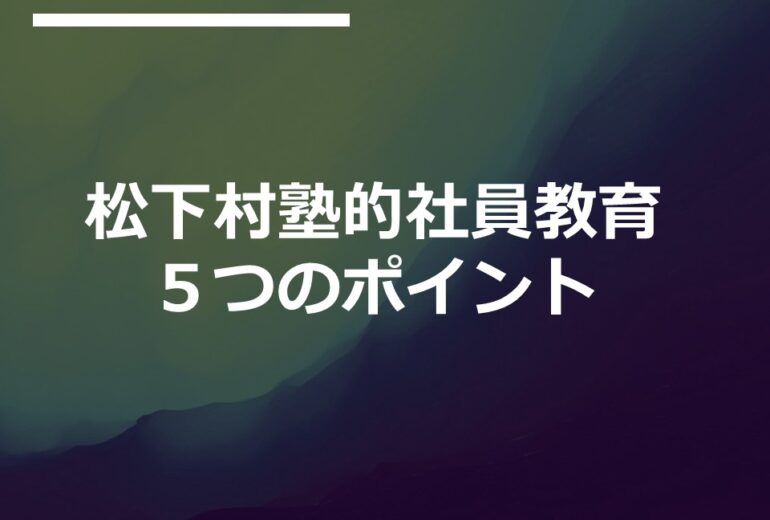

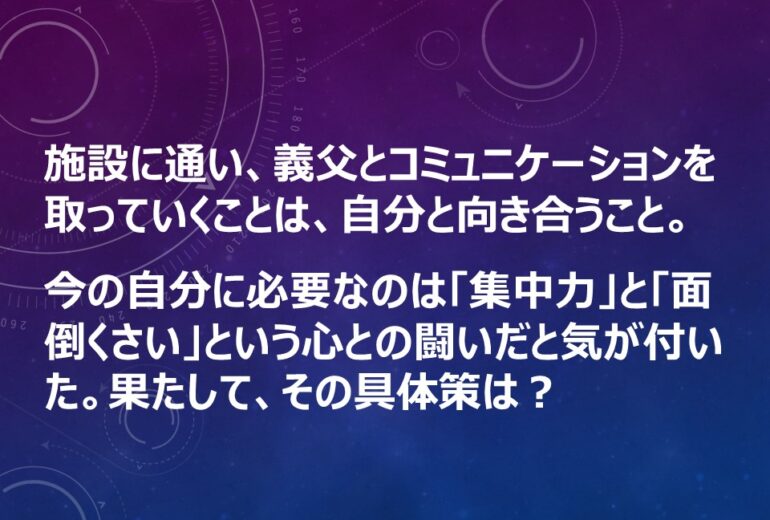
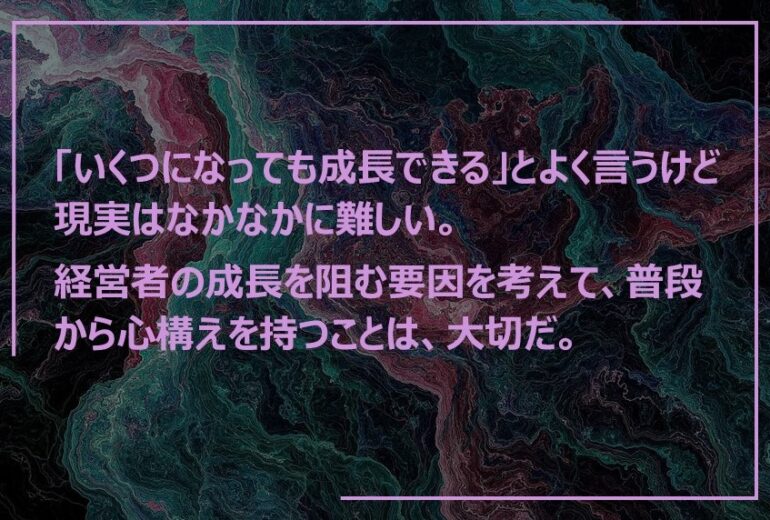
コメント