すぐ前のブログ投稿で「シニアが輝く組織へ──Shared Leadership、Co-learning、そして“現場感の回復”」と題して、シニアが活躍する場づくりの3つのことについて書きました。書きながら、そして組織ラジオでこのテーマを話しながら、「このテーマで自分が講義するとしたら、どんな内容になるだろうか」と考えていました。思うままに書いてみたら8回シリーズになりました。ご覧ください。
シニアが“活躍し続ける人材”になるための8回の講義
第1回:変化する社会と“これからの働き方”
・社会構造の変化(人生100年時代、技術革新、価値観の多様化)
・「現役を終えた後」のキャリアが長くなることの意味
・役職・年齢ではなく「価値提供」が軸になる働き方へ
・シニア世代に求められる“自己変容力”
第2回:キャリアの棚卸しと“価値”の再定義
・自分の経験やスキルは、どこにどんな価値があるか?
・過去の成功体験が“時代遅れ”になっていないかを確認する
・「私はこうしてきた」ではなく「今の現場は何を求めているか」
・“自分語り”を“他者支援”に変える意識の転換
第3回:共に学ぶ姿勢 ― コ・ラーニングのすすめ
・「教える側」から「学び合う仲間」へ
・若手から学ぶ/若手に学ばれるシニアとは
・恥をかいても学ぶ、失敗しても問い直す姿勢が信頼を生む
・「学び続ける大人」であることの尊さ
第4回:アップデートする力 ― テクノロジーへの向き合い方
・デジタルに苦手意識がある人こそ「入り口の工夫」が必要
・「できない」ではなく「できるようになる」ために何が必要か
・DX時代に必要な“最低限のデジタル素養”
・学び方が分かれば、年齢は関係ない
第5回:組織で活躍するための“人との関わり方”
・上から目線/過去語りになっていないか?
・「聞いてもらえるシニア」「一緒に仕事したいシニア」とは?
・貢献は“指示”ではなく“支援”のかたちで
・傾聴力と謙虚さが最大の武器になる
第6回:“自分の役割”を変化させ続ける柔軟性
・マネジメントだけが価値ではない
・伴走型アドバイザー、プレイヤー、メンター、サポーター…多様な役割
・必要に応じて「一歩引く力」「一歩出る勇気」
・「主役にも脇役にもなれる人」が組織を支える
第7回:自分自身の健康・モチベーション管理
・働き続けるために“心と体のメンテナンス”が土台
・「自己肯定感」×「社会との接点」を維持する
・健康習慣、学習習慣、対話習慣のつくり方
・「人に会う」「動く」「新しい刺激を受け取る」
第8回:社会とつながり、役立つ喜びを持ち続ける
・「働く」ことは「価値提供し続ける」こと
・経済的な理由だけではない“仕事の意味”
・世代を超えて役立つ存在になることの幸福
・最後に:これからの生き方・働き方をどう描くか
———————————————————————
なんの解説もなく、タイトルと内容のイメージだけなんですが、どうでしょう?
色々な思いが湧き上がってくるかもしれません。
講義+ワークショップ形式で、できれば実際に若手との交流や、経験棚卸のワークなんかもできるといいですね。
機会があれば、具体化してみたいと思います。
組織ラジオでも語っています
この講義リストについて、組織ラジオをでも語り合っています。
ぜひお聴きください。下の番組タイトルをクリックしていただくと、ポッドキャストに飛びます。
■第237回組織ラジオ「シニアが“活躍し続ける人材”になるための講義リストを作ってみた」





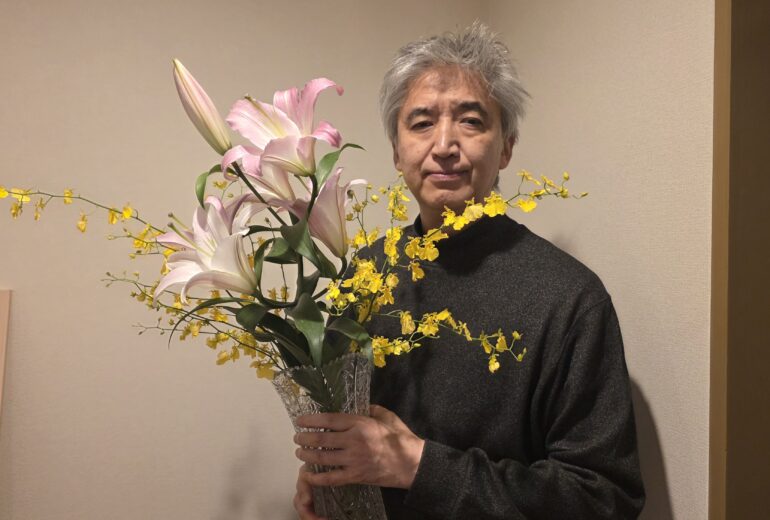
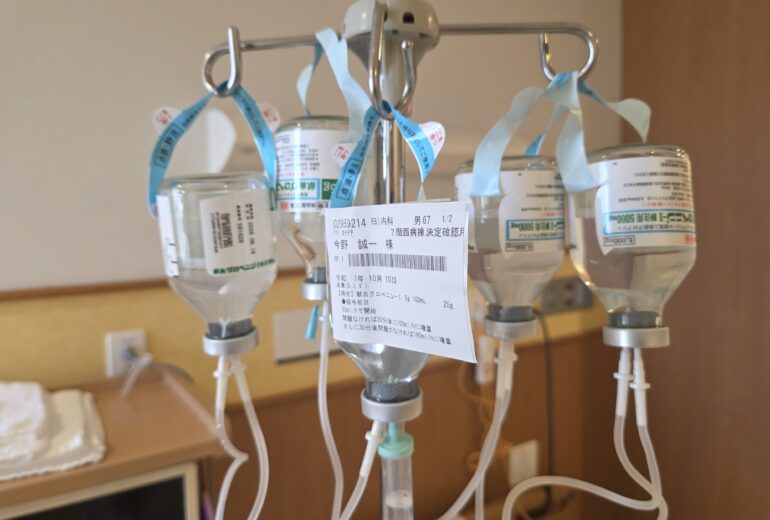
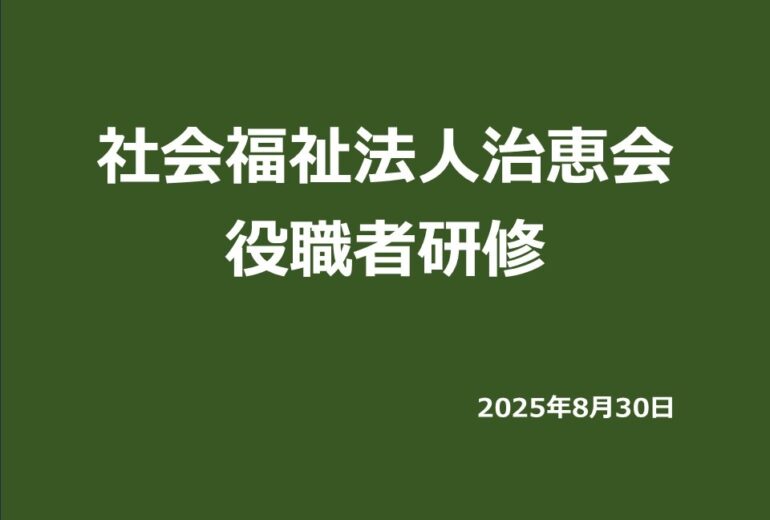
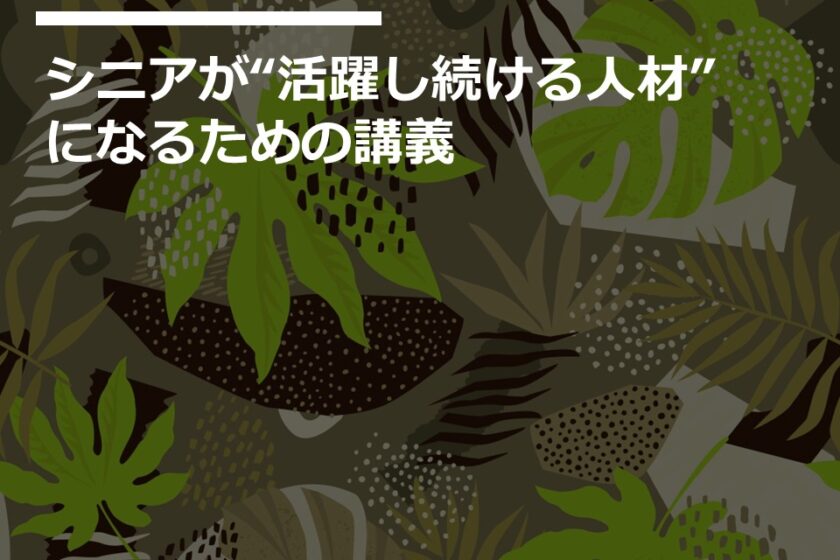







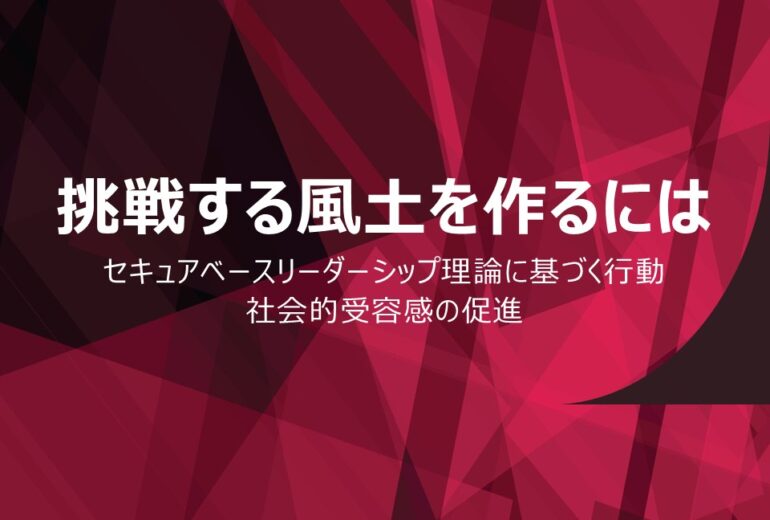
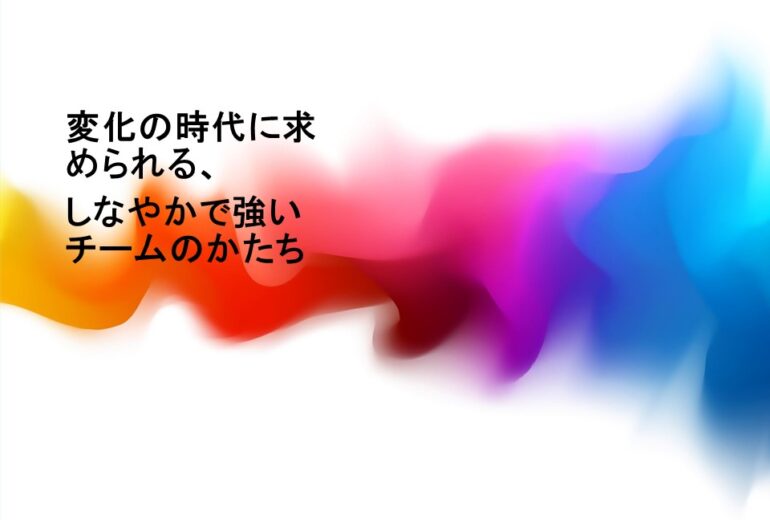
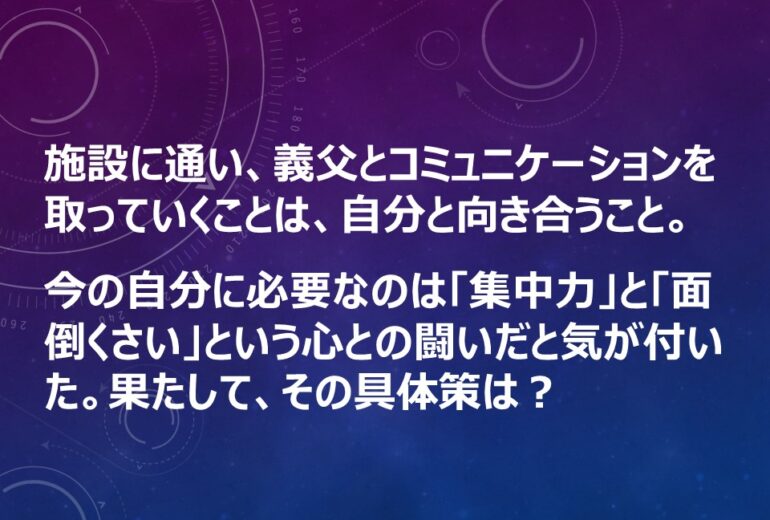


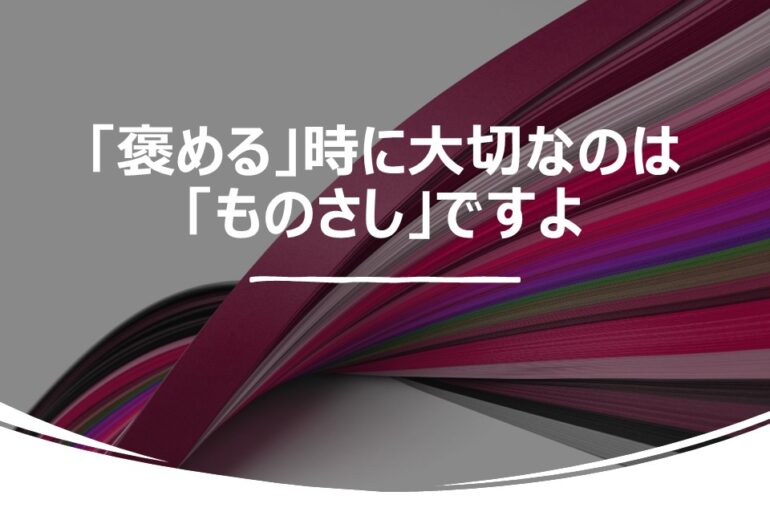

コメント